
服とか、おもちゃとか、絵本とか、子供が使ったり遊んだりする物って増えがちで、片付けが面倒ですよね。
今このブログを読んでいる方の中で、このような子供が使う物の片付け方や整理整頓の仕方がわからなくて困っているという方は、いらっしゃいませんか?
今回は子供に関わる物が散らかっていて困っている方に、子供服や絵本やおもちゃの片付け方や収納の仕方について、紹介します。

LINE登録期間限定キャンペーン中!】
どうしてこんなに子供の物は多いのか?
子供が生まれるまでは子供の物がこんなにも多くなるとは考えてもみなかった、というかたも多いのでは?
なぜ子供の物って、多くなってしまうのでしょうか?
成長のスピードが早い
あなたにはこんな経験はありませんか?
そんなに久しく会ってない人に自分の子供を会わせた時に、「まあまあ、こんなにも大きくなって」と言われたこと。
あなた自身は毎日子供と目を合わせているので、そこまでは感じないけど、やたらいろんな人から大きくなったと言われること。
これって、それだけ子供の成長するスピードが早いということなのです。
成長するスピードが早いと、それだけ次から次へと、服を買い足していかなければなりません。
どうでしょう、子供さんが大きくなって、もう着れなくなった服をまだ家の中にそのままにしていませんか?
思考の形成時期
生まれてから思春期を過ぎるあたりまでの時期は、子供さんの思考や嗜好の形成の時期と言われています。
なので、好き嫌いや興味の移り変わりの変化が大きいことがあります。
例えば、つい最近まで特定のおもちゃで遊んでいたのに、今は全く遊ばなくなって、違う別のおもちゃで遊び始めたようなこと。
毎日毎日同じ絵本を読んでいたのに、ある日突然ぱったり読まなくなって、違う絵本を欲しがり始めたというようなことがあります。
そうなってくると、もはや遊ばなくなったおもちゃや、読まなくなった絵本が増えてくるのではないでしょうか?
そういった物がそのまま家の中にあったら、次から次へと買い足してくる物と合わさって、どんどんと物が増えていってしまいます。
周りは優しい大人達で溢れている
祖父母や親戚の人たちってすごく優しいのです。
そういった優しい大人達が、次から次へと物を子供に買い与えてしまうと、どんどん物が増えていってしまいます。
あなたの子供の周りには、優しい大人達が溢れていませんか?
子供の行動をよく観察してみる
以上のようなことが重なって、子供の物は増えていくと考えられます。
では、どうすれば子供の物を整理整頓できるようになるかと言うと、最初にすべきことは「子供の観察」です。
親であるあなたは、今も十分に子供を見ていることだと思いますが、さらに掘り下げて子供の観察をしてみましょう。
具体的にどんな部分を観察するのかというと、子供の行動や意識の方向です。
例えば、以前はAという絵本を読んだり、親に読んでと頼んでいたとします。
しかし、ある時からAという絵本を読まなくなったり、読んで欲しいと頼まなくなったとします。
代わりにBという絵本に興味を示し、読んだり読んで欲しいと頼んできたとします。
それこそが、思考や嗜好の移り変わりなのです。
おもちゃに至っても、同じようなことが言えます。
ある時まではCというおもちゃで一生懸命遊んでいたのに、次第に頻度が減り、遂には触れることもなくなり、代わってDというおもちゃで遊び始める…
こういった子供の思考や嗜好の移り変わりの観察が、この後紹介する具体的な子供の物の片付けや収納の仕方に、大きく関わってきます。

LINE登録期間限定キャンペーン中!】
3つの子供の物の片付け・収納方法
それでは、増えてしまいがちな子供の物の片付け方や収納の仕方を紹介します。
子供服の片付けの方法
どんな物や場所を片付けたり整理整頓したりする上で、一番肝心なのが物を捨てるということです。
上で書いた通り、子供の成長のスピードは驚くほど早いです。
なので、ついこのあいだまで着られていた服が、今ではもう着られなくなったということがあります。
ということで、この着られなくなった服をピックアップしていき、処分していきます。
このサイズは着られないという服を集めて、汚れているような服があれば捨てたり、雑巾やウエスの変わりとして使いましょう。
ブランドの物やまだ着られる服に関しては、身近に着られそうな子供さんがいらっしゃるママ友にあげたり、お金に変えたいと思ったら古着屋さんに売ったりインターネットオークションに出品してみましょう。
インターネットオークションのことに関しては、「オークションで不用品を売る時に知っておくべき3つのこと」や、「どうすれば高く売れるか?ガラクタを高価買取してもらう方法」に、詳しいことを書いているので、参考にしてみてください。
さて次は、これからも着る服を収納していくのですが、ここでのポイントは「着る頻度」です。
頻繁に着る服を、タンスの引き出しの奥の方にしまっておくと、取り出しにくいですよね?
着られないいらない服を処分した後は、これからも着る服の頻繁別に分けていきましょう。
頻繁別に分けられたら、よく着る服は取り出しやすい場所へ、あまり着ない服は比較的取り出しにくい場所へ収納するようにしましょう。
服の収納についてもっと掘り下げた方法が知りたい方は、「着たい服を早く見つけられる、クローゼットの片付け・収納のコツ」や、「シワの心配バイバイ!服の片付け方と収納方法」を参照してみてください。
おもちゃを片付けるコツ
おもちゃの片付け方に関しては、まずは上で書いた「子供の行動をよく観察してみる」を実践しましょう。
子供がおもちゃで遊んでいるその行動を、よく観察してみてください。
すると、あなたの子供が遊んでいるおもちゃは、大まかに3つに分けられることに気づくと思います。
- 「よく遊ぶおもちゃ」
- 「そこそこ遊ぶおもちゃ」
- 「あまり遊ばないおもちゃ」
ひょっとしたら4つだったり2つだったりするかもしれませんが、数はあまり問題ではありません。
その遊ぶ頻度や興味の有無で分けられたグループごとに、それぞれおもちゃ箱を用意して、その中にそれらのグループで分けられたおもちゃを収納していってください。
すると子供の側からしてみても、よく遊ぶおもちゃがひとつの箱の中に全て収納してあるので、取り出しやすく遊びやすいですし、子供自身がおもちゃを片付けることも簡単になると思います。
※子供自身におもちゃを片付けさせるための収納方法を知りたい方は、「踏んでケガする心配がなくなる、おもちゃを棚に片付ける方法」を読んでみてください。
そして分けられたおもちゃのグループの中の「あまり遊ばないおもちゃ」の箱は、子供が取りにくい場所に収納しておきます。
ここからが肝心で、その場所を少しずつ少しずつ遠ざけていくのです。
すると、そのままその「あまり遊ばないおもちゃ」の存在を忘れてしまうかもしれません。
ひょっとしたら思い出すかもしれません。
いずれにせよ、子供の「あまり遊ばないおもちゃ」への意識を徐々に薄めさせていくのです。
そして、良い頃合いを見計らって、その「あまり遊ばないおもちゃ」でまだ遊ぶかどうかを、子供自身にジャッジさせるのです。
このジャッジを親がしてしまうと、子供の自尊心を傷つけたり、子供の判断能力が伸びないことになります。
なので、このジャッジは子供自身にさせてください。
そこで始めて子供が「いらない」と言った物に関しては、捨てたり処分をしたりができます。
絵本を片付ける方法
絵本の片付けに関しては、おもちゃの場合とほぼ同じ方法をしてみてください。
子供の絵本の興味を観察し、興味別のグループに分けて、興味のある絵本は取り出しやすくしまいやすい場所へ、興味のあまりない絵本の置き場は徐々に遠ざけていって、最終的なジャッジを子供自身にさせましょう。
最終的に子供自身が片付けられるように
親がやりやすい片付けや収納をしたら、子どもにとっても片付けやすい環境が出来上がるというメリットがあります。
皆さんも、ぜひ試してみてください。
不用品回収サービスの詳細はコチラをご覧ください。

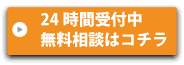





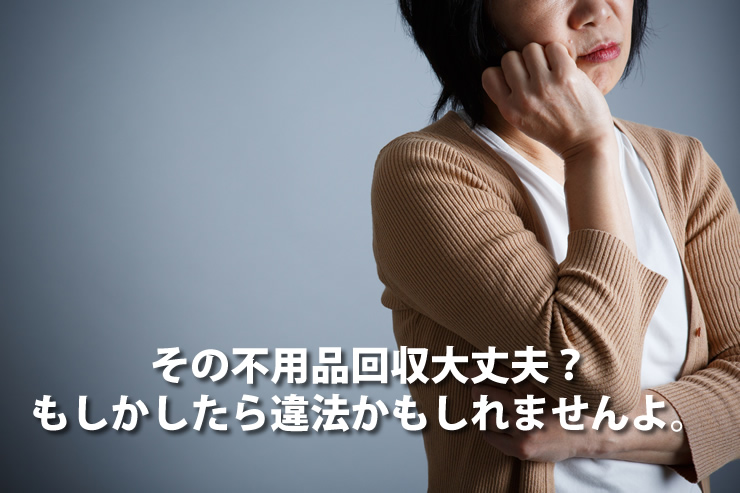


即日お片付けサービス
業者を選ぶなら「業者紹介サービス」が一番安心です。すぐに片付けをしてほしい!でもどこに相談してもすぐに対応してくれない…。初めての業者選びだからどこに相談すれば失敗しないか?ネットで検索したら業者にボッタクられたという記事を見た…。など、不用品回収業者選びについてお悩みではありませんか?
結論から書きますが、片付け・不用品回収業者を選ぶなら「業者紹介サービス」を選ぶことをオススメします。業者紹介サービスでも「片付け110番」が一番。- ご要望を即時解決!
- 最大1億円の賠償責任保険加入済
- トラブルにも仲介
- 安心保証制度
- 徹底した加盟店教育制度
- お客様限定キャンペーン実施
ご要望を対応、保証もすべて完備しているからです。片付け110番へご依頼頂きました声も合わせてすべてご案内します。