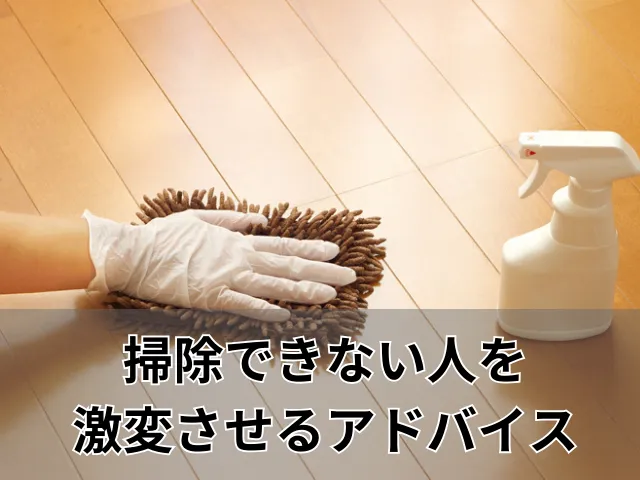
仕事が終わって疲れて家に帰ると、妻と子供たちが笑顔で出迎えてくれる、明るくて居心地のよい家。
男性誰もが、思い描いている家庭像があると思います。
幸せな家庭像を思い描いて誰もが結婚しますが、結婚して家庭生活を始めたら、想像していた結婚生活とはずいぶん違っていたと、嘆いている男性もいるかもしれません。
例えば、こんな人はいないでしょうか?
家の中はいつも物が散乱し、掃除がされていない部屋にはゴミや埃、洗濯物がたまり、風呂場はカビだらけ、トイレや台所が臭い状態なのに、奥さんが家の掃除をしないことで困っているという人はいませんか?
自分は仕事で忙しくて家のことはあまりできないし、いくら『掃除をしてほしい!』と頼んでも、奥さんが掃除をしてくれないということは、なかなか人に相談できず、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
掃除できない人、片付けられない人が、一念発起して断捨離をするという人が増えています。
モノであふれかえっていた部屋が、断捨離をしたらすっきりと片付けられ、その状態がずっと続いているという人の事を、テレビで紹介されていたのを見たことがあります。
断捨離をするには、すべてのものを分類する作業なので、1日2日でできるものではなく、ある程度の期間が必要です。
家中のモノを全部出して、必要なものと不必要なものを分けて、不必要なものを処分していくのですが、それは1度、家の中がひっくり返ったような状況にしてから、置き場所を決めて、必要なものをすべて分類していくのです。
モノが散乱していた部屋が、見違えるようにキレイになった変わり様と、断捨離をした人の晴れ晴れとした顔が、とても印象的でした。
断捨離をした人は、『もう以前の部屋には戻りたくない』と言っていました。
断捨離をすることは、思い切りが必要です。
もの捨てられなくて家が片付けられない人にとって、捨てるという作業は、自分自身が抱えている問題や何かと決別するというような、大きな決断の連続です。
断捨離の片付け作業からも分かるように、家の掃除や片付けというものは、自分と向き合っていく作業でもあるのです。
自分と向き合うことに、掃除ができるようになる糸口が隠れています。
そこで今回は、奥さんが掃除ができなくて困っている人のために、掃除ができない人の特徴や原因と、奥さんが掃除ができるようになるためのアドバイスの方法について、紹介します。

LINE登録期間限定キャンペーン中!】
掃除できない人の特徴
掃除できない人の性格には、特徴があります。
自分が掃除ができない人に多い性格に当てはまっていて、実際に掃除ができないとします。
その場合は、掃除ができない性格の特徴を理解し、意識して取り組むことで、掃除ができるようになる道を開くことにつながります。
性別
掃除をする脳力には、男女の差はありません。
男女によって脳の構造が違うため、得意不得意の分野があるとは言われますが、掃除が得意か苦手かという理由には当てはまりません。
女性の脳の特徴
女性の脳は男性の脳よりも、右脳と左脳をつなぐ脳梁が太いことが多く、女性は脳梁が太いことで左右の脳の切り替えが得意なので、多くのことに気を配ることが得意であると言われています。
女性は部屋の汚れた部分によく気が付いて、家のあちらこちらをキレイにするのが得意かもしれませんが、同時に多くのことに意識が向くので、気が散って掃除に集中できないという人もいます。
男性の脳の特徴
逆に男性は一般的に脳梁が細いので、左右の脳の切り替えが女性ほど得意ではないので、1つのことに集中することが得意である人が多いです。
男性は細かいところに気づきにくいかもしれませんが、掃除に集中し始めれば、やり遂げる能力は女性よりも高いということになります。
掃除ができない女性の方が問題になるのはなぜ?
テレビなどで、掃除ができない女性のことが取り上げられることが多いですよね。
女性の方がよく問題視される理由は、家事全般はもちろん『掃除や片付けは女性が担当するものである』という、役割分担に関する日本人の古くからの考え方が、根底にあるからです。
昔は、女の子は子供の頃から良いお嫁さんになるように、掃除片付けをしっかりするように躾(しつ)けられて育てられていました。
女性は部屋をキレイにしておくもの、というイメージが一般的に浸透し、掃除ができない女性の問題の方がインパクトが強く、クローズアップされて話題にのぼるため、掃除ができないのは女性の方が多いと思われやすいのです。
掃除をしない男性や部屋が汚い男性は、男だからという理由で、気にされないことが多いのです。
子供の頃からの習慣の差
それでは、掃除が得意な人と苦手な人との差は、どこで出るのでしょうか?
掃除ができるかどうか、人によって差があるのは、子供の時からの習慣の差にあります。
インターネットによるアンケートリサーチ会社の統計によると、子供の頃、家がキレイに掃除されていた人は、大人になっても高い割合で、自分の家をキレイにしているという結果が出ています。
母親が掃除ができず、いつも散らかった実家で育った人は、大人になって家庭を持ち、家を管理する立場になった時も、部屋が汚くても気に留めることなく、育った環境と同じように、掃除をしないようになることが多いのです。
掃除が苦手な親は、子供に掃除や片付けを教えることも、ほとんどなかったでしょう。
逆に、いつもキレイに片付いている清潔な家で育った人は、家が汚くなると、どうにも居心地が悪くなって、掃除をしないではいられなくなります。
家をキレイにしていた親は、子供にも掃除や片付けの方法を教えながら育てたに違いありません。
性格
インターネットによるアンケートリサーチ会社では、掃除ができない人の性格に関するアンケートも実施されていました。
性格の特徴で、傾向の割合が高かった性格の順に、紹介します。
モノが捨てられない
ものが捨てられないのは、部屋を片付けられない人の大きな特徴です。
ものを溜め込んでしまうと、大量のものを片付ける場所がなくなってしまいます。
置き場所のないものは、その辺に無造作に置かれるか、散らかして置かれているほかに置き場所がありません。
たくさんのものがあって散らかっている状態では、掃除が非常にしづらくなり、自然と掃除が苦手な人になってしまいます。
ものをたくさん持っているのに、部屋をいつもキレイに掃除している人は、よっぽど掃除が得意な人だと思った方が良いでしょう。
持ち物の管理ができない
物をたくさん持っている人は、自分が持っているものを把握しきれず、自分の持ち物の管理が出来なくなります。
自分が持っているものを把握していないと、同じようなものを買い足して、さらに物を増やしてしまうという悪循環に陥ってしまいます。
また、ものの管理ができていないということは、ものの収納場所も決められていない状態であるになります。
収納場所が決まっていないことは、自然と片付け下手になってしまいます。
物事の決断に時間がかかる
ものの片付けや物の管理は、ものに対する決断の連続です。
- 必要か、必要ではないのか。
- 捨てるのか、捨てないのか。
- どこに、どうやって収納するのか。
その場で決めなければ、部屋は片付きません。
『後で決めよう』と思った時点で、部屋はもう散らかり始めているのです。
そして更に、散らかっている部屋を見て『掃除をするか、しないか』という決断を、掃除が苦手な人は『後で掃除しよう』と思ってしまうのです。
掃除をしようという決断が、後に後にと何度も先延ばしされるたびに、部屋は掃除されず、汚い部屋を維持することになってしまいます。
時間にルーズである
『約束の時間や期限を守る』というルールを守れない人は、『汚いから掃除や片付けをする』という、掃除の基本ルールを守ることも苦手です。
掃除や片付けをすることに対する優先順位や価値観が低く、「めんどくさい」という気持ちや、「自由に時間を過ごしたい」という欲求の方を優先させてしまいます。
心理状態
『人の心はその人の部屋に表れる』と、よく言われます。
掃除ができない人の心理状態には、何らかの問題を抱えていることがよくあります。
心理状態だけでなく、身体の問題から掃除ができない場合もあります。
心は身体とつながっているので、心理状態、身体の状態は、掃除のやる気と、それぞれ影響し合っているのです。
具体的な心の状態について、3つ紹介します。
モノで心の問題を埋めようとしている
家中がものであふれていて、掃除ができなくなっている人の中には、本人が気が付いていなくても、心に問題を抱えている場合があります。
ものを捨てられない人や、ものをたくさん買ってしまう人の深層心理には、愛情不足、悲しみ、空虚感のような心の穴を、もので埋めようとしている場合が多いのです。
心に虚しさを感じている人の口癖は、『寂しい』『悲しい』『つまらない』というものです。
夫婦間や親子間の関係が悪くて、愛情を求めているということがあるかもしれません。
悲しみやつらい経験の記憶が、いつも心の奥底にある可能性はないでしょうか?
自分自身の価値や、人生の生きがいを感じられず、いつも虚しい気持ちがあるということも考えられます。
もし、心に問題があるのであれば、問題に向き合って解決していくことで、心をもので満たそうとする欲求を抑え、ものを減らして掃除ができるような環境にすることが解決の糸口です。
心や身体が疲れている
心身が疲れているために、掃除ができない人もいます。
精神的に追い込まれている場合があるので、掃除が手につかないことを、その人のSOSとして捉えることが、必要な場合もあります。
子育て中の主婦は、365日24時間子供や家族の世話をして、家事をするのは疲れるものです。
親の介護をしている人も、同じように疲れています。
働いている奥さんは、仕事と家事の両立をすることは、とても疲れることです。
精神的なストレスある場合も、心や身体を疲労させます。
ストレスや身体の疲労で疲れている人は、掃除をする気力が出てきません。
心身ともに元気になるような生活の工夫をすることで、掃除に対するやる気を上げていくことが必要になります。
休みの日はご主人が子供の世話を引き受けたり、悩みを聞いてあげたりして、奥さんの疲れを取ってあげて下さいね。
好きなことだけしていたい
「嫌いなことはしたくない」という人は、「掃除がめんどくさいのでしたくない」、という人がいます。
子供の頃から我慢しないで育った人や、逆に非常に強いストレスを受けて育った人の中には、我慢する力が弱い人がいます。
成長の過程で形成された性質は、自分で自覚して改善しようという気持ちが必要になります。
我慢できないという性質を自覚した上で、掃除することを自分の『訓練』だと捉えて、「掃除をしたくない」という、気持ちを乗り越えられるように取り組むことが必要です。
ゲームやスマホを長時間使っている人の中にも、我慢する力が弱い人がいます。
『ゲームばかりしている子供は、キレやすくなる』という話を、聞いたことがありませんか?
ゲームやスマホなどの画面ばかりを見ていると、脳の機能が低下し、我慢する力が落ちてしまうからなのです。
我慢する力が足りないと感じる場合は、まずは、ゲームやスマホを使う時間を減らしましょう。
そして、積極的に運動することを習慣にすることによって、脳の我慢する力を改善することができます。
掃除ができないのは病気なのか?
掃除ができない人の中には、病気を抱えている場合もあります。
掃除ができない病気の中には、生まれつきの脳の機能障害の場合と、ストレスなどから引き起こされる、後天的な病気による場合があります。
掃除ができない人が抱える病気である、ADHD、強迫性貯蔵症(ホールディング)の場合は、生まれつきの脳の機能障害で、うつ、セルフネグレクト、統合失調症、認知症は、後天的な疾患とされています。
ストレスなどから引き起こされた病気の場合は、早く治療すれば治る場合も多いので、『掃除ができないことが、もしかして病気のサインであるかもしれない』と考え、早めに医療機関を受診し、治療を始めて回復すれば、また掃除や片付けができるようになります。
ADHDの場合は、片付けられないことが本人のストレスになっていることが多いので、積極的に治療や手助けをすることで、掃除や片付けができるようになります。
うつや認知症の場合は、一緒に掃除や片付けをすることで、症状の改善を助けることにつながります。
どの病気にしても、治療やカウンセリング、周りの理解と病気に応じて適切な援助が必要なので、家族の人の対応方法についても、医療機関で指導を受けるようにしてください。
極端に掃除や片付けができない場合に疑う主な病気には、以下のようなものがあります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)
『片付けられない症候群』とも呼ばれるADHDの人は、『不注意』『多動性』『衝動性』という疾患の症状の特徴により、片付けをすることが非常に苦手です。
『片付けをしなければいけない』思いながらも、どうしても片付けらず、困っていることがきっかけで、ADHDであると診断される大人が多いのが、この病気です。
強迫性貯蔵症(ホ―ディング)
『溜め込み症候群』とも呼ばれる『強迫性貯蔵症』の人は、常に家の中に物を溜め込んで、家がゴミ屋敷のようになってしまいます。
『保有したい』という強力な感情があり、物を手に入れないと大きな不安を感じたり、この先2度と手に入らないと考えてしまい、手に入れないと後悔するだろうと、強迫的に思ってしまいます。
うつ
ストレスなどが原因でうつになると、興味、意欲、精神活動などが低下し、掃除や片付けなどは、どうでもよくなってしまうことで、部屋が汚くなります。
自分をコントロールすることが難しくなり、掃除や片付けそのものに手がつきません。
部屋が散らかることで、うつ病が更に悪化するという、悪循環にはまってしまいます。
セルフネグレクト
セルフネグレクト(自己放棄)とは、自分に関心がなくなり、生命維持の意欲が低下して、自分自身さえ世話をできなくなる状態になる病気です。
ストレスなどが原因でセルフネグレクトになると、掃除片付けどころか、きちんとした食事さえも取らなくなってしまいます。
ゴミ屋敷に住んでいる人の中には、セルフネグレクトの人も多いといいます。
統合失調症
統合失調症とは、20~30歳代に多く見られる認知・行動・情動などに障害が起こるという精神疾患です。
場合によっては、ものを溜め込んだり、ものを集めたりして、部屋の掃除ができなくなってしまう場合もあるようです。
認知症
脳の機能が低下することで、日常生活が困難になります。
意欲や段取り力などが低下するため、掃除ができなくなり、部屋が散らかるようになります。

LINE登録期間限定キャンペーン中!】
『掃除できる人』に激変させるアドバイスの方法
掃除が全くできない人が、掃除ができる人になるためには、少しずつ段階を経て変わっていくことで、振り返ってみると激変するほど掃除ができるようになっていることを目指すのが得策です。
急激に変化した習慣は急激に元に戻りやすいものですが、時間をかけて1歩1歩掃除を習慣化して、確実に変わっていくことで、掃除習慣を身につけることができるのです。
劇的変化のために必要なのは、まずは小さな現実的な1歩からです。
努力すれば掃除ができるようになるのかを知っておくために、掃除ができないことが病気によるものではないことを確かめておくためにも、心配であれば、まずは病院を受診しておきましょう。
もし病気が理由で掃除ができないのであれば、医療機関の助けや治療が必要になります。
掃除ができない原因を考える
掃除ができるようになるために、まずすべきことは、奥さんが掃除ができない『原因』を、奥さんと一緒に旦那さんも一緒に考えることです。
掃除をしない奥さんに対して、「いいかげんに掃除して!」とか「こんな簡単な掃除もできないのか?」 というように、責めてしまいがちです。
しかし、責められた方は「自分は掃除ができない人なんだ」など、やる気が削がれたり、傷ついてしまい、かえって逆効果です。
奥さんの話をよく聞いて、掃除ができない原因を、あらゆる方面から一緒に考えてみましょう。
この記事で紹介した、掃除ができない人の『性格面』や『心理面』の内容を、掃除ができない原因を探すために参考にしてください。
掃除ができない原因が分かれば、その原因を取り除く方法も考えることができます。
具体的な環境の改善や、掃除方法の見直し、手助けの方法などの工夫をすることで、掃除ができるようになる手助けになります。
掃除をする目標を持つ
『掃除や片付けができるようになりたいという気持ちを持つこと』が、掃除ができる人になるための必要な条件です。
掃除をしたいという意思は、他人から「掃除をして!」と言われただけで、持てるものではありません。
本人が掃除をしたいと思うような、ぴったりな目標を一緒に探してみましょう。
目標や、こうなりたいという夢が、掃除をするための原動力になります。
掃除をしてどんな自分になりたいのか、どんな気持ちで暮らしたいのか、という心理面へアプローチをして、目標を持つことは有効です。
または、家に親しいお客さんを呼ぼうとか、憧れの部屋の写真を探してそれを目標にするといった、具体的で分かりやすい目標を持つことが向いているタイプの人もいます。
掃除をしてどうなりたいかという目的を持った時に、先を見通す力や、未来に対する希望といった、前向きな力が生まれ、その力が掃除をするモチベーションへとつながっていきます。
一緒にじっくり取り組む
掃除ができない奥さんの場合、どうしても他の人の助けが必要です。
1番の助け手になるのは、旦那さんです。
もし旦那さんが、「自分はダメ男だから、奥さんへのアドバイスはどうしてもできない」という場合は、民間の家事代行サービスや、掃除や片付けのアドバイザーを頼んで、奥さんが掃除ができるようになるように、定期的にアドバイスしてもらいましょう。
まずは夫婦共通の、掃除の行動目標を持ち、ルール作りをします。
基本的には部屋の『整理・整頓・掃除』をすることで、『清潔な家と住み心地のよい家』を目指すのですが、そのためにすべきことを、細く項目にして、1つずつ目標として設定します。
1つの掃除の良い習慣が身についたら、次のステップに進むというように、旦那さんがリードすると良いですね。
目標とする項目とは、例えば『ゴミはゴミ箱に入れる』『食事が終わったらお皿を洗う』『1週間に1度は掃除機をかける』というようなことです。
旦那さんが担当する掃除場所も決めて、そこをキレイに掃除することで、奥さんは「手伝ってくれている」と感じて、やる気アップにもつながります。
片付けに関しては、収納場所を決めて収納するものの名前書いてを貼っておくという、『ラベリング』するという作業を一緒にすると、非常に効果的です。
奥さんが掃除ができるようになるために、旦那さんが一緒に取り組んでいく時に気をつけることは、掃除や片付けの主役は奥さんであって、旦那さんは助け役に徹するということです。
奥さんの主体性を引き出すように、まずは本人が掃除しやすい所から掃除の習慣を身につけるというように、奥さんの達成感や自信を身につけることにも、気をつけてくださいね。
けなさずに褒める
奥さんの掃除のやる気を引き出し続けるためには、褒めることが重要です。
人は他の人から褒められたり、感謝されることで、やる気や達成感、幸福感を感じます。
逆にけなされると、やる気を失い、傷ついてしまいます。
ですから、掃除ができる奥さんになってもらいたいと思っている旦那さんは、奥さんが少しでも掃除ができたらほめるなど、チャンスがあれば、ことあるごとに褒めるようにしてください。
掃除ができたという『行動』を褒め、できないことができるようになったという『能力』を褒め、掃除をしてくれたという嬉しい気持ちを『感謝』して表現するなど、バリエーションを広げて、褒め方にも気を配るようにすることが必要です。
まとめ
掃除や片付けが、まるでできないという奥さんがいて困っている、という人のために、奥さんが掃除ができるようになるための方法について、書いてきました。
掃除ができないということは、ただ掃除をサボっていると思われがちですが、もしかしたら病気や深刻な問題が隠れている場合もあります。
掃除ができないということが、そのサインになっているかもしれません。
ですから、ただ掃除ができるようになって欲しいというだけではなくて、掃除ができない原因を突き止めて、それを一緒に解決していくことこそ、本当に掃除ができる奥さんに激変させることができるのです。
相手を自分のように思いやって、つらいことがあれば一緒に乗り越えていくことが、愛する奥さんを救い、夫婦関係を深めていくことにもつながります。
掃除ができない奥さんを、掃除ができるようにするには、本人も含め旦那さんの大きな努力が必要ですが、掃除ができるようになることに取り組むことを通して、旦那さんの愛情を確かめられる時でもあるのです。
掃除ができる奥さんになるように応援しながら、ステキな家庭を作り、居心地のよい家も作っていってくださいね。

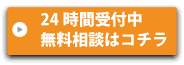









私は シングルマザーで、主人は居ません。褒めてくれる人は子供だけです。それでも片付けられません。どうしたら良いのでしょうか?
小さい子供が3人も居るので、お金は掛けられません‥早く片付けられる様に成りたいです。
おうちの広さ、状況にもよりますが、掃除が出来ない方のほとんどが「習慣化できていない」ことが多いです。
最初は「ここだけ」という感じでもいいので、10分、20分という時間を決めて毎日お掃除されてみてはいかがでしょうか?
まずは1ヶ月に1つ、それができたら次の月にはもう一箇所、という感じで進めてみると、習慣化もしやすくなります。
うちは掃除が出来なくて嫌な物は押し込むかどこかに隠す癖があり、私が指摘したら、私が出来てない事を引き合いにだして、離婚寸前です…
>私が指摘したら、私が出来てない事を引き合いにだして…。
みなさん同じようなお悩みを持たれてますね…。
私達の家庭は複雑で、遠縁の両親は強制結婚。結婚処か恋愛に無関心。母は結婚6ヶ月で布団の中に画鋲を撒かれる等、父にDVを受け続けた。 私達娘はおぞましい存在だと思っていた。父は「女の子はギャーギャー泣いてうるさいから要らない」 二卵性で女の子だけ産まれた。父「こんなの要らない。付録(妹の私)迄付いて来た」と激怒。私達も虐待が始まった。 戸籍上は4人、実際は母子家庭と同じ。 母も片付けは苦手だったと…。 私達も父によく怒られてた。父は私達3人が邪魔。殺されそうになった事も…。 内気な性格になり、中学生頃に人生を捨てた。苛めで自殺を促された。死のうと思ったけど、出来なかった。 23歳になる年、父は母に「出て行きたかったら出て行っていいよ。…」そして家出という形で母子3人は離れた。 私達がまだ10代の頃、追い出し親戚を呼び暮らす計画をしていたと40代になり姉から聞いて知った。 今思えばあんな毒父がいるのに、何故片付けが出来なかったのかと思う。現在地区担当員にプレッシャーをかけられ、片付けをしている。残して置きたい物も捨てるしかない。厄介なのは中身が残っているであろう、殺虫剤スプレー缶。雑誌に吹き掛け、無理に使いきるしかない様だ。 現在精神科通院しながら姉妹で生活している。 担当員も片付けに関して、本当に精神的負担を増やす言い方をする。かなり辛い。
「片付けしたいのに片付けできない!」というのは、悪いことではないと思います。人には心理機能というのがあり、個性があります。一見すると「よくない点」は「悪い」と思われがちですが、違う面からすると「良い」ともとれることがあります。心理機能については近々測定法をアップしますのでお待ちくださいね。
私は家族と同居で統合失調症ですが、片付け・家の掃除を全てしています。
統合失調症の人は、掃除ができないのは本当なのですか?
精神病だからといっても治療を受けてなければ掃除ができる状態ではないと思いますし、薬の副作用でできない人もいると思います。精神病だからといって、掃除ができないと決めつけるのは誤解なんじゃですか?
掃除ができないと決めつけられるのは心外です。
大変失礼しました。記事を修正しております。